 にこぞう
にこぞう絶景ポイントに着く前に、ケツの痛さで「もう帰りたい」と思った経験…皆あるよな?
最高の景色を眺め、風を切って走る開放感。誰もがツーリングに求めている最高の瞬間です。しかし、その至福の時間を突然「激痛」が襲うことがあります。そう、ライダーの永遠の悩み「おしりの痛み(ケツ痛)」です。
「もう無理だ、休憩だ…」と、何度も楽しみに水を差された経験があるのではないでしょうか。ライダーの体格や車種に関係なく、誰にでも起こり得る現象。単なる「慣れ」や「根性」の問題でもありません。
本記事では、私自身も悩まされてきたケツ痛の原因(圧迫・振動)を解説します。さらに、「お金をかけずに今すぐできる休憩・姿勢の工夫」から、「高性能クッションや最終手段のシート加工」まで、具体的な解決策をステップ別に紹介します。
この記事を読み終える頃には、あなたのツーリングは「苦行」から「快適な旅」へと変わっているはずです。
なぜおしりは痛くなる?(原因がわからないと対策も打てないよね)



「行きは天国、帰りは地獄…」 最高のツーリングを、ケツの激痛が邪魔するんだ!
バイクで長距離ツーリングをすると、おしりが痛くなりがちですよね。あれは一体何なのでしょうか。一見ふかふかそうなクッションであったとしても、ツーリング時間が長くなるにつれて、おしりはどんどん痛くなります。
「行きはよいよい、帰りは怖い」ではないですが、ツーリングの前半で良い景色を眺め、いい気分で運転していたのに、帰りは目に涙を浮かべながらおしりの痛みを我慢して帰路についているライダーも少なくないはずです。だって、僕もそうでしたから。
じゃあ、これはなんでこんなにもおしりの痛みがあるんでしょうか? 主に以下の2つが大きな原因として考えられます。
血行不良と振動による複合的な影響
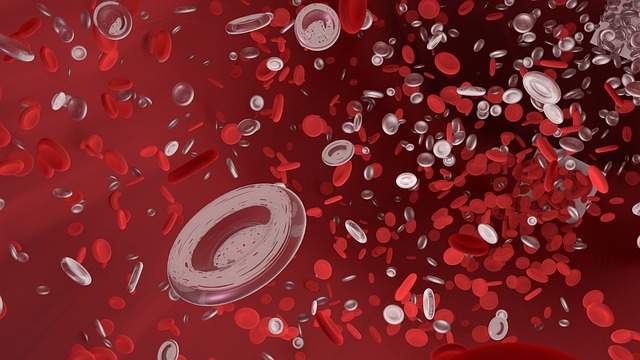
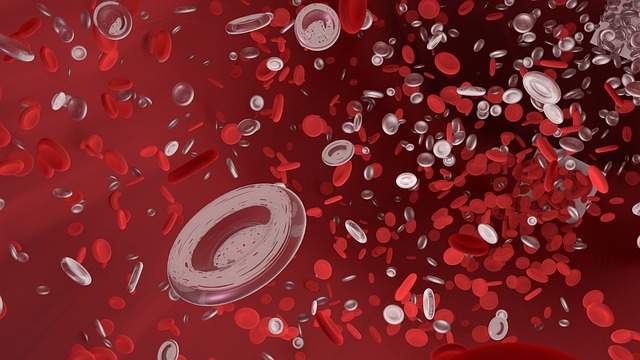
私たちがバイクのシートに座っているとき、体重のほとんどは坐骨(ざこつ)と呼ばれる骨の先端で支えられています。硬いシートに長時間座り続けると、この坐骨周辺の皮膚や筋肉、そして血管が強く圧迫されてしまいます。
これが血液循環の悪化、すなわち血行不良を引き起こし、おしりの痛みとなります。
どんなに柔らかでフカフカなクッションでも、血行不良になってしまえば、痛みは発生します。極端かもしれませんが、高級なソファに8時間座り続けていたら、きっとおしりは痛くなるでしょう。


しかもバイクは着座位置をずらすことは困難。背もたれも手すりもないため、全体重がおしりに一極集中する環境にあります。一度座ったら座りっぱなし。それ故に、バイクとケツの痛みは相性が良くなってしまう、いやな相性なのです。
さらに、バイクは車以上にエンジンの振動や路面の凹凸(段差を超えたときの衝撃など)が、体全体、もといおしりにダイレクトに響きます。衝撃は体の関節(膝や肩など)で逃がすことは可能ですが、これがうまくいかないと、おしりに「どん!」という衝撃が入ることがあります。これもおしりにダメージが蓄積される要因の一つです。(そう考えると、車ってすごいですよね。快適な乗り物だ…)
痛みを加速させる「シートの硬さ」


車種にもよりますが、バイクシートが硬すぎるというのも、おしりが痛くなる要因の一つです。
これは想像するに容易いと思います。ソファの上で1時間座るのと、コンクリートの上で1時間座り続けるのは、どちらが苦行でしょうか? 百人いたら百人が正解できるでしょう。正解は「コンクリートの上で1時間座り続ける」です。
逆に柔らかすぎるシートも、腰が沈み込み過ぎて疲れやすそうな気はしなくもないですが、やはり硬ければ硬いほどおしりにかかる負担は大きくなります。
バイクシートがソファのようなフカフカな素材になることはありえないので、硬すぎるバイクシートや、ローダウンのために「あんこ抜き」されたシートなどは、おしりが痛くなってしまう大きな要因となるわけです。
【いますぐできる】ツーリングの快適性を高める実用的な対策グッズ



ケツ痛の原因はわかった。さっさと金をかけずに解決するか、金をかけて快適性を買うかだ!
ケツが痛い…これは1章で説明したとおり、血行不良が主な原因です。ということは、血流が悪くなりにくいように、シートクッションを改良すれば良いというシンプルな話になります。多くのライダーがイメージしているとおり、ここで登場してくるのがシートクッションという対策アイテムが肝となってきます。
ツーリング時のケツ痛対策のド定番「ゲルザブ」の導入


「バイク お尻 痛い」なんて検索すると、高確率でゲルザブの記事が出てくることでしょう。これは、バイクのおしり対策として有名な、ど定番中の定番商品です。
ランニングシューズでもゲルが内蔵されていたり、その技術が使われていたりすることからもわかる通り、対衝撃性には定評のある素材です。しかも柔らかい。


僕自身もランニングを趣味としていますが、ランニング時に膝にかかる衝撃は体重の3倍にもなると言われています。その衝撃を和らげる素材や技術としてシューズにゲルが使われている通り、衝撃吸収やクッション性はゲルの得意分野。
だからこそ、バイクシートとの相性も抜群です。ゲルザブの導入は、多分、バイクのケツ痛対策として最高峰クラスの対処だと呼べるでしょう。ただ一つ言えるのは、少々値段が張ること。そこに目をつぶれば、ゲルザブの右に出るものはいないだろうと感じます。
シート装着ではなく「履く」タイプを選ぶという選択肢


シートに装着するゲルクッションとは別に、インナーパンツ(履くタイプ)とゲルが一体型になっている商品も発売されています。
デイトナから出ているスパッツとゲル部分が一体型になっているタイプは、ゲルザブより安価なため、手が届きやすい価格帯なのは嬉しいところです。
別の商品ですが、ハニカム構造を有したゲルクッションを持っているので座り心地は想像できます。最初は若干の違和感はあると思いますが、すぐに慣れるので問題ありません。
ライディングパンツの下にすでにロングタイツ・ロングスパッツを履いている人はスパッツの二重履きとなるため、ユーザーは選ぶかもしれません。しかし、スパッツやタイツのような締め付け感が大丈夫な人であれば、この履くタイプは非常におすすめできる対策グッズです。
【お金をかけない】今すぐ実践!ライテクと休憩の工夫でケツ痛を回避



いやだ!お金はびた一文出したくない!「慣れ」と「テクニック」でケツ痛をねじ伏せるぞ!
ケツが痛いからといって、誰もがすぐに高価なゲルクッションを購入できるわけではありません。(といいながらも、本当はゲルクッションがあると劇的に快適になるので、心の底では推奨したいのですが…)
とにかく!ここでは、お金をかけず、今の愛車とあなたの体だけでできる神対策を紹介します。ケツ痛は血行不良が原因であると説明したとおり。であれば、血流が悪くならないようにすればいいのです。
脳筋的な発想?「慣れ」を味方につける(ツーリングは筋トレ論)


シートが硬いなら、その硬さに耐えられるようにケツに筋肉をつければいい…そんな脳筋的な発想も、個人的には嫌いではありません。
ちょいと冗談も入っていますが、人間の身体は過酷な環境下であっても「慣れる」という構造をしています。ケツが痛くても何度も何度も経験すれば、痛みにくい体(と姿勢)へと徐々に変化していきます。
適切な筋力(体幹や足腰の筋力)は、振動を逃がしたり、正しい姿勢を長時間維持したりするために非常に重要です。「ツーリングは筋トレ」と捉え、短距離から徐々に距離を伸ばしていくことで、「慣れ」を味方につけましょう。
停車時こそ最大のチャンス!血流を完璧に回復させる


ツーリング中は一切合切おしりをずらすことができない…なんて環境は少ないはずです。血流が悪くならないようにすればいいのだから、こまめな「休憩」と「動作」がケツ痛対策として有効です。
- 信号待ちでは「おしりを浮かす」
- 停車時はバイクに座りっぱなしではなく、両足で立つなんてことも有効です。僕はこれをかなりしているせいか、ケツが痛いとはあまり思ったことがありません。一度完全に立ち上がることで、圧迫されていたおしりの血流を完全に回復させることができます。
- 休憩の目安
- バイクから降りる休憩は、「○時間に一度」と具体的な目安を決め、強制的にバイクから降りておしりを解放しましょう。
- 停車時は「おしりを完全に離す」
- 両足だちはもちろん、安全な場所であればスタンドを立てて腰を浮かすなど、停車時はしっかりとおしりをシートから離し、血流を完全にリセットさせることが重要です。
秘技!ライディング中の「チマチマ・シフト」


もちろん信号がない場所もあるでしょう。そんなときは、秘技スタンディングドライブ!…ってのは危ないので行いませんが、一瞬おしりを浮かすくらいはできると思います。
これらはおしりが痛くなる前にチマチマと行っていれば、血行不良になりにくくなります。意識的におしりの位置を左右、前後に細かくシフトすることで、圧迫箇所を変えるだけでも効果があります。
これらを行っていても結果的にお尻は痛くなるかもしれませんが、ケツ痛を感じ始める時間を後ろ倒しにできれば、次の休憩スポットまでノーケツ痛状態を保てるのです。ケツ痛の延命こそ、ツーリング全体を通して痛みを最小限に抑えるための重要な戦略です。
【究極対策】シート加工・交換を考える(高コスト・最終手段)



究極の快適性を追求するなら、もうシートそのものを切り刻むしかないのか!?
ここまでは「お金をかけない方法」や「シートに後付けするクッション」を紹介してきましたが、中にはシートそのものを加工しているツワモノもいます。ケツ痛対策の究極、そして最終手段と言えるでしょう。
シートの加工とは、シートの表皮を剥がし、中のクッション材をくり抜いてゲルクッションを埋め込んだり、形状そのものをライダーの体型に合わせてカスタムしたりすることです。
なぜシート加工・交換を推奨しないのか


僕自身はあまりバイクのカスタムが好きではありません。ノーマルマフラーで十分ですし、チェーンを特殊なものに変えたり、フェンダーレスにしたりもしません。ノーマル状態で十分で、この状態が一番好きだからです。
バイクで走ること、行ったことのない土地に行くこと、都心ではなく人や建物が少ない自然豊かな場所に行くことの方が大好きです。
車でも行けますし、車の方が快適ですが、道中を楽しめるのはバイクだと思っています。車だと行き先(ゴール)にたどり着いてからがスタートですが、バイクは、たどり着くまでの苦労・大変さ・辛さ・不便さを経験し、その壁を乗り越えてたどり着くことそのものが、かけがえのない時間となる。そんな魅力を醸し出せるのがバイクの良さだと感じています。
そんな哲学から、カスタムにはあまり興味がありません。
加工は「勇気とコスト」が必要な難易度の高い選択


シートの加工は、技術的な敷居が非常に高いのが現実です。
例えば、シートを切ってゲルを内蔵させるにしても、素人には荷が重すぎます。 シートを切るって、なんだかバイクに悪いことをしているみたいで…勇気がいることですよね。
一旦破って、加工して、改めてシートを綺麗に張り直す…。そんな道具も知識も経験も有していません。
知識・経験・道具・お金、これらすべてを考えたら、プロの業者に依頼するか、もしくは「普通にゲルザブを購入する」という選択肢が、費用対効果の面で最も優れている、というのが僕の結論です。
異論!なぜ「排気量アップ」がケツ痛対策になるのか?


シート加工以外に、ケツ痛対策として究極的に有効なのは、「排気量アップ」という選択肢です。これは冗談ではなく、排気量が上がることで、主に以下の2つ対策が同時に実現する傾向があるからです。
排気量が大きいバイクは、設計時点から長距離走行を前提としています。そのため、シートの面積が広がり、クッション材の量が増え、素材も疲れにくいものが採用される傾向が強いです。250ccクラスの車種とは、シートの「作り込みのレベル」が根本的に異なってくるのです。
一般的に、排気量が上がると、エンジンの振動が「減る」というより、おしりに響く「振動の質(周波数)」が変化します。単気筒や小排気量車に特有の細かく体に残りやすい高周波の振動が減少し、長時間座っていても疲れにくい振動特性になることが多いのです。
もちろん、これは高コストな選択ですが、もし乗り換えを検討中なら、「シートの作り込み」はケツ痛対策として重要な判断基準になるでしょう。
【異論!】ローダウンのための「あんこ抜き」はケツ痛を加速させる?



待て!足つき性を良くするための「あんこ抜き」は、確実にケツ痛を加速させるということを忘れるな!
ここまで様々なケツ痛対策を見てきましたが、もう一つ、ケツ痛の是非を問うべきカスタムがあります。それが「あんこ抜き」です。多くのライダーに恩恵をもたらす手法ですが、こと「ケツ痛対策」という観点から見ると、実は相性が良くないのも事実。
あんこ抜きの目的と、隠されたデメリット


まず、大前提として「あんこ抜き」という手法に対して異議を唱えたいというわけではありません。あんこ抜きをして足つき性が改善され、安全にバイクに乗れるようになったライダーも多くいるはずです。
あんこ抜きとは、バイクシートのクッション材をくり抜いて薄くする手法を指します。なぜわざわざクッションを抜くのでしょうか。その理由は、足つき性をより良くするためです。シートが薄ければ薄いほど、地面までの距離が短くなります。そのため、低身長な方や女性などは、あんこ抜きをして足つき性能を良くする…なんてカスタムをすることがあります。
しかし、ここで思い出してほしいのが第1章で解説したケツ痛の原因です。シートの中のクッション材を抜いてしまうわけですから、シート自体が薄く、硬くなります。
クッション材が減る=おしりにかかる圧力を分散するものがなくなるということ。当然、より「おしりが痛い…」という結果になりかねません。
どちらを取るべきか?


おしりの痛みと足つきの良さ。どちらを取るべきかと言えば、これは絶対に足つきの良さを取るべきです。ライディング中のケツの痛みは耐えられますが、停車時の不安や立ちゴケのリスクは、それ以上の危険をもたらすからです。
ただし、あんこ抜きを行う場合は、「ケツ痛が加速する」という注意点があることを頭の片隅に入れておく必要があります。このデメリットを打ち消すために、ゲルクッションやインナーパンツを履いたりといった対策が不可欠となるわけです。
【まとめ】ケツ痛を乗り越えて、楽しいツーリングを!
今回は、多くのライダーが悩む「ケツ痛」の原因から、コストをかけない応急処置、そして究極の対策までを解説しました。
ケツ痛は、坐骨への「圧迫」と「血行不良」が引き起こす、避けがたい問題です。しかし、適切な対策を講じるだけで、ツーリングの快適性は劇的に向上します。
最後に、この記事で紹介した対策を、あなたの「状況」に合わせて再整理します。できることから実践してみてください!
状況別:ケツ痛対策の再整理
| カテゴリー | 対策の具体例 | 特徴と効果 |
| 今すぐできる対策 | 信号待ちで両足で立つ、ライディング中におしりの位置を細かくシフト、こまめに休憩を取る。 | コストゼロ! 血流をリセットし、痛みの発生時間を後ろ倒しにする延命策。 |
| 標準的な解決策 | ゲルザブなどのシートクッション導入、履くゲルパンツの活用。 | 根本的な圧迫を分散・吸収し、長距離での快適性を確保する最も現実的な解決策。 |
| 特別な状況への対応 | あんこ抜きをしたシートに、ゲルクッションの併用(または内蔵加工の検討)。 | 足つき優先のカスタムによるケツ痛加速を抑えるための、やむを得ない追加コスト。 |
ツーリングの目的は、景色を楽しみ、道を走る喜びを感じることです。「おしりが痛い」という苦行を乗り越えてこそ、その喜びは大きくなりますが、道具やテクニックで楽ができるなら、それに越したことはありません。
ぜひこれらの対策を試して、あなたのツーリングをもっと快適でかけがえのない時間にしてください!








コメント